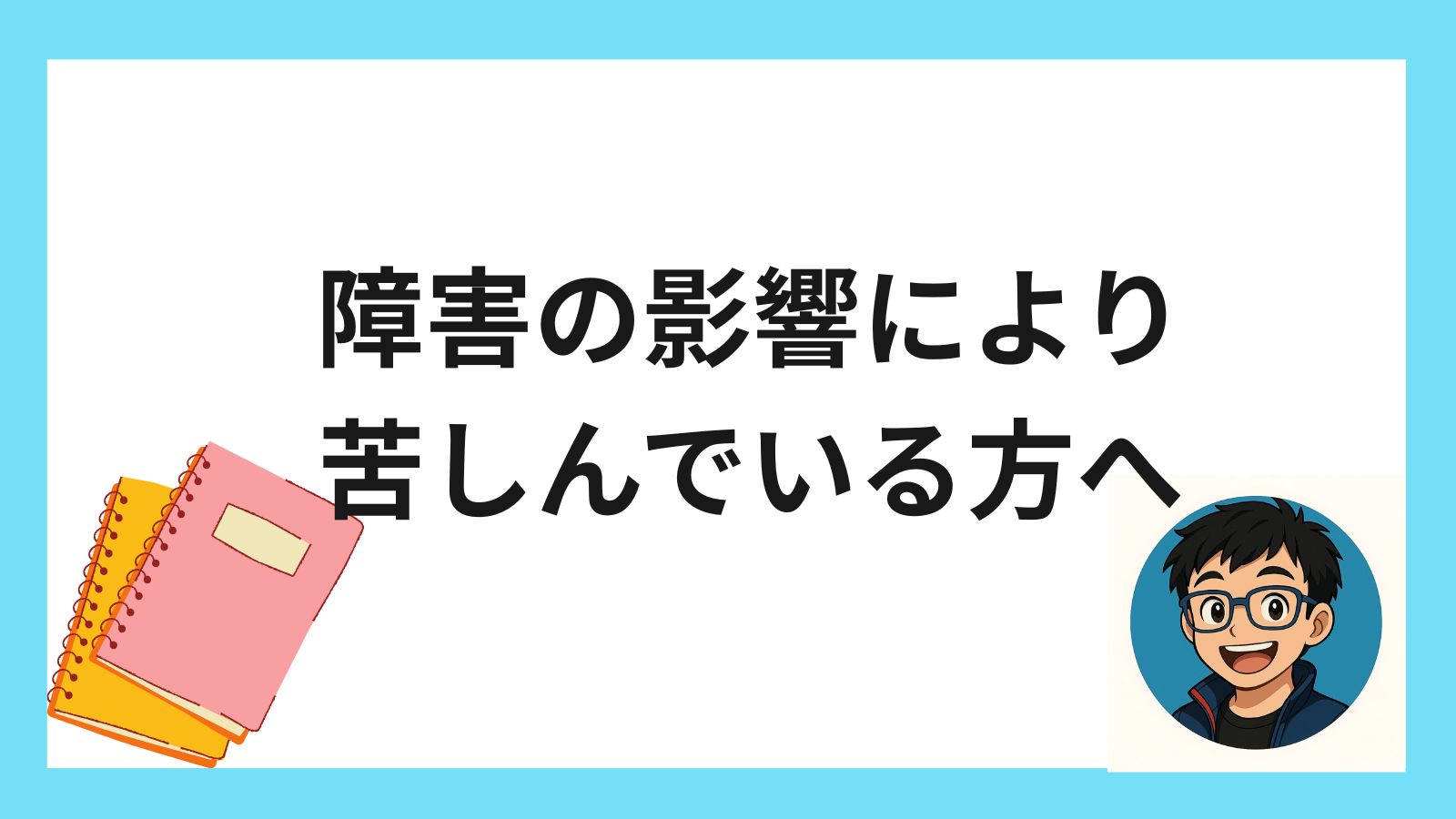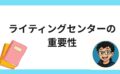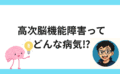はじめに
私は右半身麻痺と高次脳機能障害という障害を抱えながら、大学生活を送っていました。
特に、移動やノートを取るといった日常の学びの動作が難しく、支援を求める必要がありました。
大学1年次、講義での代筆支援を希望しましたが、障害コーディネーターに相談しても認められませんでした。支援が受けられないまま、2年間は一人で受講し、試験や課題に挑むしかありませんでした。
自分なりの努力と結果
それでも私は諦めず、自分なりにできることを精一杯行い、学業に励みました。
結果として、多くの科目で「秀」や「優」の成績を取ることができました。
沖縄大学の場合(目安)
秀=100点から90点
優=90点から80点
良=80点から70点
可=70点から60点
不可=60点以下〜
真面目な性格が功を奏したのか、評価は高く、学びを深めることができたと感じています。
とはいえ、すべてが順調だったわけではありません。
大学4年間の中で、2回だけ「不可(落単)」の評価を受けた科目がありました。
1回目の「不可」:社会理論と社会システム
内容が難解で理解が追いつかなかった
1年次に履修した「社会理論と社会システム」は、社会福祉士の資格取得を目指す在学生向けの専門的な科目でした。
私は「人体の構造と機能および疾病」「心理学理論と心理的支援」といった他の2科目では非常に興味を持ち、しっかり学べましたが、「社会理論と社会システム」は内容が抽象的で難しく、理解が追いつきませんでした。
必修ではなかったため、「この1科目を落としても進級に支障はない」とあったので、思い切って諦める決断をしました。
苦手なものに固執するよりも、得意分野を伸ばすことに集中した方が、自分にとってはプラスだと感じたからです。
2回目の「不可」:健康福祉レクレーション論
代筆が必要だと実感した出来事
2年次に履修した「健康福祉レクレーション論」は必修科目でした。事前にこの科目は「不可率が非常に高い」と聞いていました。
講義としては、その教授でもペースが早過ぎて、口頭だけ述べていて、焦りや苛立ちが常にありましたが、何としてでも良い成績を残したいことや、レクレーションとして講義自体は興味深く、私はどれも皆出席であり、テストも真面目に取り組み、手応えもあり自信を持って提出しました。
ところが、結果はまさかの「不可」。大きなショックを受けました。
このとき私はようやく再び障害コーディネーターに相談し、「代筆支援をお願いしたい」と強く要望しました。すると、やっと支援が認められ、来年の後期に再履修できることになりました。
代筆サポートを受けて挑んだ再履修では、「可」の評価を得て無事に単位を取得。
3年次に進級できたときの安堵感は、今でも忘れられません。
支援を受けることの大切さ
この経験を通じて、私は「努力だけでは乗り越えられないことがある」と痛感しました。
そして、支援を求めることは「甘え」ではなく、自分の力を活かす手段であるということも学びました。
4年次になると、高次脳機能障害の認知が進んだのか、「社会福祉特殊講義」(前期・後期)も代筆の申請がスムーズに通るようになりました。
特に、「社会福祉士の資格取得に向けた特殊講義」でも代筆が可能となり、合計で3つの講義で支援を受けながら学べる環境が整いました。
振り返って伝えたいこと
当時は、障害への理解がまだ不十分だったのか、最初の2年間は孤独で苦しい思いをしました。
それでも、「自分ひとりで頑張ること」も大切ですが、「必要な支援を適切に求めること」も同じくらい大切だと、今なら思えます。
支援を受けたからこそ、私は大学生活を最後まで続けることができ、卒業することができました。
まとめ:これからの挑戦へ
この経験を通して、私は次の2つのことを心に刻みました。
- できないことに固執せず、できる方法を探すこと
- 必要なサポートを遠慮せずに求めること
大学生活の中で得たこの学びを、これからの人生でも活かしていきたいと思います。
困難に直面したときこそ、「工夫」と「支援を受ける勇気」が大きな力になります。